Event イベント

7月26日(土)、あわいひかり編集部の地元、観音寺市の小学生とその保護者15組34人のみなさんと観音寺市有明浜にてビーチクリーンイベントを開催しました。
当日は、かがわ海ごみリーダーとして活躍されている安井里香さんと田中真利子さんのお二人をお招きして、地元の浜辺がどのような状態なのか?海ゴミはどのくらい流れ着いているのか?そのゴミはどこから、どのようにして流れてきたのか?などなど、実際に浜辺に出て海ゴミを拾い、そして海ゴミについて学び、それを活かす楽しいイベントとなりました。
〜Event1:海ゴミを拾う〜
今回のビーチクリーンイベントは「海ゴミを拾う」「海ゴミについて学ぶ」「海ゴミで創る」の3部構成で行われました。まず、海ごみリーダーの安井さんと田中さんから海ゴミ拾いに関する留意点や注意事項の説明を受けた後、参加者全員で有明浜へ出て、15分程、浜辺に流れついたさまざまな海ゴミを回収しました。炎天下の中、参加者全員でたくさんのゴミを回収することができました。
ペットボトルやパッケージのフィルムをはじめ、ロープやライター、釣具などの全国的によく見られる海ゴミに混じり、瀬戸内海の海ゴミの特徴である「豆カン」と呼ばれる牡蠣の養殖に使うプラスチックの筒がたくさん回収されました。
参加した子どもたちは、海ゴミはどこから流れてくるの?どうして海にゴミを捨てるの?などといった純粋な疑問を海ごみリーダーや保護者に投げかけていました。
〜Event2:海ゴミについて学ぶ〜
有明浜にて海ゴミを回収した後は、場所を観音寺市総合コミュニティセンターに移し、かがわ海ごみリーダーの安井さんを講師に、海ゴミについての勉強を行いました。
地元香川県の浜辺や海岸などに打ち上げられたゴミの種類や、どこからどのようにして流れついたのか、流れついた海ゴミはどのくらいあって、どのように回収されているのかを教えていただきました。
香川県だけでも海岸に漂着するゴミは約150トン、海を漂流しているゴミが約24トン、海底に堆積したゴミは約325トン。合わせると約500トンもの海ゴミが存在するということです。
海岸に漂着した海ゴミの内容としては、ペットボトルやプラボトル、ペットボトルの蓋などが全体の30%を占めていて、食品の包装袋やプラスチック袋が7%、食品容器や食器が9.9%、その他のプラスチック類が18.6%、発泡スチロールが20.2%、その他、金属やゴム、木、紙、ガラスなどがありますが、圧倒的にプラスチックゴミが多いことがわかっています。
そのようなプラスチックゴミは、海岸や浜辺の景観を損なうだけでなく、海で暮らす生物にも深刻な被害を与えているということです。例えば、捨てられた網にあざらしや魚、海亀などが絡まってしまったり、海鳥が誤ってストローや豆カンなどのプラスチックゴミを雛に与えてしまったりすることで、野生生物への被害が広がっている事実なども教えていただきました。
参加した子どもたちも真剣な眼差しでスライドを眺め、時折メモを取りながら安井さんの講義に聞き入っていたのが印象的でした。
〜Event3:海ゴミで創る〜
講義の後は、田中さんが講師となり、有明浜で拾った貝殻やガラスなどの海ゴミを使って「海ゴミ貯金箱」を制作しました。
既成の貯金箱を紙粘土で包み、そこへ貝やガラスなどを自由に飾り付けることで、自分だけの貯金箱が完成しました。
海ゴミを拾って、学ぶだけでなく、ゴミを使ったワークショップを実施することで、参加した子どもたちに楽しみながら海ゴミについて考える機会を設けることができました。
参加した子どもたちからは「海ゴミと一緒に貝殻を拾ったことが楽しかった」(辻井瑛登くん)、「初めてのゴミ拾いは大変だったけど、また海をキレイにしたいので参加したい」(新田恵さん) 、「拾った貝殻を使った貯金箱作りが楽しかった」(三宅桃太くん) 、「海ゴミを拾うのは大変だったけど、貯金箱を作るのは楽しかった。海のゴミの勉強にもなった。」(森本莉乃さん)などの声を聞くことができました。
3時間程度の短いイベントではありましたが、瀬戸内の海ゴミ問題について知っていただけたのではないでしょうか。
〜Epilogue:さいごに〜
ビーチクリーンイベントを終えて、今回講師として参加いただいた、かがわ海ごみリーダーの安井さんと田中さんにお話をお伺いしました。
あわいひかり:今日はありがとうございました。とても楽しく勉強させていただきました。ところで、かがわ海ごみリーダーとはどのような活動をされているのですか?
安井さん:海ごみリーダーは会社員や主婦、ダイバーや観光ガイドなど、さまざまな職種の方々が香川県の海を守ろうと、今回行ったようなビーチクリーン活動や海ゴミについての出張講義、ワークショップなどをボランティアで行っています。
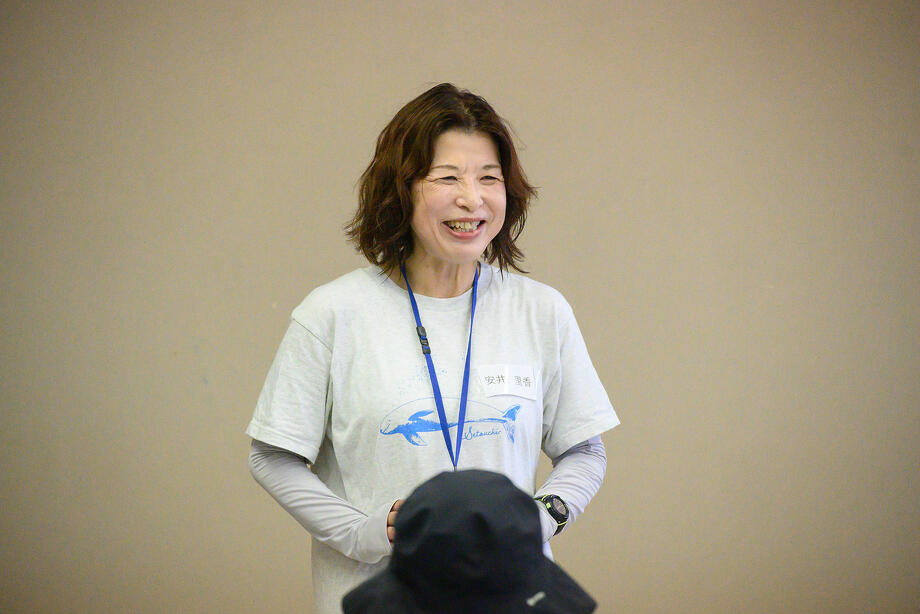
かがわ里海大学が海ごみリーダーになるきっかけだったという安井里香さん
あわいひかり:どういったきっかけで、お二人は海ごみリーダーになられたのですか?
田中さん:幼い頃から貝殻やシーグラスを拾うのが大好きで、拾いに行くたびにゴミが多いなって感じて。ちょっと嫌な気分になったので、そのゴミをどうにかしたいと思ったのがきっかけです。
安井さん:私も香川生まれなので、瀬戸内海は身近だったんですが、なかなか海に行く機会がありませんでした。でも、もともと海が好きだったので「かがわ里海大学」という香川県が開催している講座に参加しました。そこで、瀬戸内海の海ゴミについての座学をきっかけに、もっと本格的に学んでみたいと思って海ごみリーダーになりました。
あわいひかり:海ごみリーダーとして、県民のみなさんや子どもたちに伝えたいことはありますか?
田中さん:香川県内でも地域によってビーチクリーンへの意識の高さはさまざまです。だからこそ、県内の学校を訪問させていただいて、海ゴミについて知っていただき、小さい頃から海ゴミについて関心を持っていただくことが大切だと思っています。また、今回のように親子で海ゴミに関心を持ってもらうことは親子間のコミュニケーションにもなりますし、海への関心や環境への意識を高めるきっかけにもなると思っています。

子どもの頃から瀬戸内の穏やかな海が大好きだという田中真利子さん
安井さん:最近では、企業のCSR活動として海ゴミ問題に取り組む事例が増えています。自らが製造する製品が環境にどのように影響しているのかということに責任を持つ姿勢は非常に重要になってきていると思うんです。実際に海ゴミを今すぐゼロにするのは現実的には難しいと思いますが、生活者が製品のパッケージや使い方を考え、責任を持って処理することが重要だと思いますし、製品を作る企業も捨てることを考えた製品設計を行って、作る方と使う方が協力して、海ゴミの問題解決に取り組む必要があると思っています。そのお手伝いをかがわ海ごみリーダーとしてやっていきたいと思っています。
あわいひかり:今日はありがとうございました。
-

取材・文
森本 未沙(海育ちのエバンジェリスト)








