Report レポート

1. 地球温暖化が東かがわの手袋産業を襲う。
2. ここがヘンだよ、アパレル産業の商慣習。
3. 笑顔を循環させたい想いから生まれたブランド「ecuvo,」
4. “プロキング”がわたしたちに教えてくれること。
5. そのSDG’s、楽しんでますか?
香川県東かがわ市は第一次世界大戦から日本の手袋産業を支える重要な製造エリアとして栄え、第二次世界大戦後は高度経済成長の波に乗り、国内外の需要を取り込みながら香川の主要産業として成長してきました。日本国内で流通する手袋の約9割が東かがわ市の手袋関連企業を通して流通されており、ファッションで大活躍のニット手袋やゴルフなどのスポーツ手袋も東かがわが一大産地です。
その東かがわで1977年に創業し、地球環境に配慮したブランド「ecuvo,」を立ち上げたり、企業全体でユニークな取り組みをおこなっている株式会社フクシンの福﨑二郎社長に、こうした取り組みの背景にある想いやSDG’sの考え方についてお話を伺いました。
1. 地球温暖化が東かがわの手袋産業を襲う。

奥田:手袋産業全体の市場の動向はどのような状況ですか?
福﨑:全盛期から比べるととても厳しいです。人口減少の影響はもちろん、気候変動で冬が以前より寒くないことがじわじわと効いています。暖冬というだけで冬の売り上げが2〜3割減ってしまいます。昔は冬の間に2〜3回、都会でもしっかりと雪が降って売り上げがグッと上がることがありましたが、ここ最近は1回あるかないかです。また傾向としてずっと暖冬なので明るい見通しは立ちません。夏もUV対策など手袋のニーズがないわけでもないのですが、やはり冬のニーズとは規模が違います。
そしてさらに影響が大きいのが「スマートフォン」の普及です。都会の通勤時間を見ると一目瞭然ですが、ほとんどの人がスマートフォンを見ています。駅のホームでも車内でも肌身離さず持っているので、冬の通勤の際は手袋であったまるよりスマートフォンを触りたい欲求の方が勝ってしまう。東京の通勤ならそこまで寒くないし、外にいる時間もそんなに長くない人が多いので、少しぐらいの寒さなら我慢してスマホをさわろうとなってしまう。もちろん、スマートフォンを操作できる手袋なども登場しなんとかニーズを満たそうと試みていますが、車内では手袋を取りたいのでやっぱり邪魔になってしまう。
地球温暖化とスマートフォンの普及というダブルパンチが本当にじわじわと手袋産業にダメージを与えていますね。
奥田:私たちの食料品業界でも人口減少はとても大きいですね。胃袋が減っていくわけですから、1日3回食事を摂るとしてもその絶対値が減っていきます。ただ食事のニーズそのものはずっとあるのでまだまだシェアを確保する余地はあると思っています。
福﨑:わたしたちも昔は雪があまり降らなくても神社で神頼みしていたらなんとかなった時代がありました(笑)。しかし今は神頼みだけでは凌げません。
2. ここがヘンだよ。アパレルの商習慣。

奥田:わたしたちのメディア“あわいひかり”でも【ファッションロス】についていろいろと情報収集を進めています。手袋産業にもこうした課題はあるのでしょうか?
福﨑:あります。ほとんど変わりません。アパレルの商品は最初から「バーゲンありき」で価格設定されています。バーゲンになると30%オフや半額なんて当たり前で、その価格でもギリギリ利益が出るように製造しないといけないわけです。さらにはアウトレットまで行き着くときもあります。しかしよく考えると、これはアパレル特有の悪しき慣習だと思います。
メーカーは毎回トレンドに合わせて商品開発を行い製造する。その度に開発コストがかかり、売れ残ると在庫を抱えたくないので処分するしかありません。そしてまた新たな開発コストが発生し、常に開発とそのための素材の仕入れ、図面起こし、製造プロセスの変更など追加コストが再び発生するため、一定の費用を見込んで価格設定をしなければならず、結果的にそれがお客様の費用負担につながってしまいます。
手袋の製造は今でも職人さんによる手作業が多く残っています。機械化できるところとできないところがはっきり分かれており、指の稼働部分の動きやすさ、着け心地の良さを意識した縫製を素人がやろうとしてもうまくできません。職人さんの技術がまだまだ必要です。その部分の効率化はできないため製造コストは常に高止まりします。しかし、手作業が大変な割には儲からないので若者がなかなか定着せず、職人さんがどんどん高齢化してしまっているのが現実です。結果的に中国やベトナムなど海外に拠点を移さなくては成り立たない状態になっています。大手も儲からないし手作業が多い産業なので参入したがらない。それでも世界的に一定のニーズがあるのでわたしたちはなんとか生き残っています。また、わたしたちは商社として活動しているので、百貨店やアパレルメーカーと直接交渉し商談を重ねることができます。大手アパレルメーカーが持つルートとほとんど変わらないため、固定概念に捉われず変化を恐れずに取り組めば、まだまだ成長の余地が多く残されている産業だと思っています。
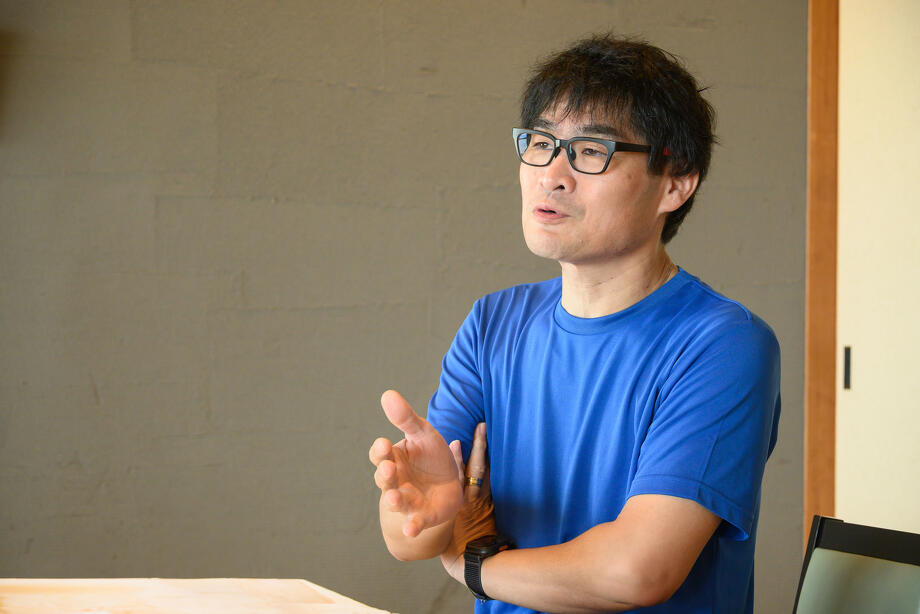
福﨑:実際にECはとても順調に稼働しています。年間約600万人のユーザーがサイトに来訪していただいており、約20万件の取引が発生しています。今や売上利益とも会社を支える事業に成長していますし、BTOBの商談の際にも「これが今売れています」というデータを示しながら商談ができるようになり、バイヤーから見ても売れ筋商品を外さずに仕入れられる安心感につながってWIN-WINの構造になっています。
3. 笑顔を循環させたい想いから生まれたブランド「ecuvo,」
奥田:なるほど、こうした新たな取り組みや既存の商流を見直す改善が功を奏しているわけですね。では環境への取り組みを全面に押し出した新たなブランド「ecuvo,」もその取り組みの一環ということでしょうか?
福﨑:そうですね。元々は2016年に私が代表に就任し、会社のインナーブランディングに取り組み始めた頃、ちょうどSDG’sの宣言がありました。いろいろと調べてみると、我々がすでに取り組んでいた社員の健康に対する考えや地域貢献のことなど多くが宣言内容と合致しているぞとなり、企業としてSDG’sを推進していこうということになりました。その際に、明るく楽しく元気よく【笑顔循環企業】を目指そうと決め、我々が笑顔で仕事をして笑顔で作った商品を笑顔で送り出し、それを笑顔で販売していただいてお客様も笑顔になる。それが我々に返ってくるという考え方で事業をやることにしました。その象徴となるのがサスティナブルブランド「ecuvo,」です。
瀬戸内海や山々に囲まれた自然豊かな環境にいるからこそ、感じる地球温暖化や環境の変化。未来も四季折々の風景が楽しめる日本であってほしいという願いを込めています。

福﨑:ご存知の通り、アパレル・ファッション業界は石油業界に次いでニ番目に地球環境を汚染しており、日本では毎分約六千着の服が捨てられています。服の廃棄量が激増する中、大量生産のためにたくさんの原材料が必要とされています。服で一番使用されている綿を栽培するには、大量の水、農薬などが必要です。地球温暖化をはじめ土壌劣化、酸性雨など環境負荷も日々増加しています。こうした悪循環を産んでしまったのはアパレル特有の商慣習にあると考え、日本人が持っているすばらしい概念である「もったいない」を意識し商品を選んで欲しいと想いこのブランドを立ち上げました。物を大切に長く使うことが一番環境にやさしく、地球もわたしたちも笑顔になる暮らしを推奨しています。
奥田:笑顔の象徴である“えくぼ”がブランド名の由来なのですね。また何より象徴的なのが【永久定番】【永久修理保証】【片手片足販売】です。
福﨑:おっしゃるとおりです。オーガニックコットンやリサイクル素材などはもはや当然なので、我々はもっと本質的なところから概念を変えようと思い【永久修理保証】をやろうと考えました。弊社は主にニット系の商品の取り扱いが多いので、結構すり減ったり破れたりしてしまいます。少しでもほつれがあったり破れたりしただけで、せっかく気に入って購入していただいているものをまた新しいものを買っていただくのはなんか違うなと。ならば、ずっとお使いいただくために永久修理保証にすることで、お客様も笑顔になるしわたしたちもそこまで商品を愛してくださるとうれしくて笑顔になる、そう考えました。
さらに商品を【永久定番】にすることで、いつまでも同じデザイン、カラーのものがいつまでも手に入るようにしました。手袋はファッションアイテムなので、トレンドや市場ニーズに合わせてデザインや素材を変えることが一般的です。一方で、このデザインがずっと気に入っていたのに気づいたら廃番になっていたということもあり、お客様のことを想うとこれもなんか違うなと感じていました。ecuvo,の商品は永久定番なので、気に入っていただいたデザインのものをずっとお使いいただけます。また永久修理保証なので永くご愛顧いただけます。さらに手袋や靴下によくあることですが、片方だけ穴が開いてしまうとか無くしてしまうといった課題もありました。それに対応するため【片手片足販売】という、業界では珍しい取り組みも始めました。

福﨑:これらのサービスを組み合わせて物を大切に長く使っていただくということが実現できるようになり、結果的にわれわれメーカーとしても同じ素材、デザイン、金型のものをずっと使い続けられるので開発コストが余分に発生せず、経営面でもサスティナブルになるという点において笑顔になり、まさに笑顔循環が実現しています。作り手としても、わたしたちの商品を長く愛してくださることはやりがいにつながり笑顔になれます。
デザインが定番なので家族全員で使おうという発想も生まれます。ファッションアイテムでそういう商品ってなかなかないと思います。子ども時代からずっと使ってきた手袋を大人になってサイズを変えて使うとか、お父さんがつかっていた手袋を子どもが引き継ぐとか、そうした習慣が定着すると「ecuvo,」というブランドがわたしたちの企業の提供価値をストレートに表現してくれる看板ブランドになると考えています。
4. “プロキング”がわたしたちに教えてくれること。
奥田:とても素晴らしいコンセプトですね。ところで福﨑さんはゴミを拾いながらランニングをする“プロキング”を長く続けておられます。今回わたしどもも実際に観音寺駅から琴弾公園までプロキングに参加させていただきました。これはどういった背景から取り組みされているのですか?
福﨑:プロギングは、ジョギングしながらゴミを拾う新しいフィットネスで、スウェーデン語の「plocka upp(拾う)」と英語の「jogging(走る)」を組み合わせた造語です。2016年にスウェーデン人アスリートのエリック・アルストロム氏によって始められました。走って健康に、拾ってエコに、新しい交流を。だれもが笑顔になりお互いを称え合えるスポーツです。この活動は瞬く間に世界中に広がり、現在では100カ国以上で楽しまれる一大ブームとなっています。日本でも、プロギングという言葉ができる前からランナーの間でゴミ拾いの活動が広がっていました。
福﨑:わたしは仕事でSDG’sを謳っているからとか、綺麗事としてゴミ拾いをしなくてはならないということは一切考えておらず「やりたいからやっている」というのが正直な想いです。
一度でもゴミを拾った経験がある人は、自らは決してゴミを捨てる人になりません。ゴミを拾えるようになると捨てないだけでなくリユースやリサイクルの意識も自然と芽生え判断基準が変わると思っています。そういう人がひとりでも多く増えていけば街からゴミを捨てる人が減り、結果的に街からゴミがなくなっていく。それこそが地球を笑顔にすることができると考えています。
奥田:福﨑さんにアドバイスをいただき走りながらゴミを拾いました。ぱっと見ただけではそれほどゴミは落ちていなかったのですが、よく見るとたばこの吸い殻やフィルムなど意外と落ちていましたね。
福﨑:ゴミは見ようとしないと見えないものなのです。ぱっと見は案外綺麗に見えるもので、拾うぞと思うとタバコの吸い殻やフィルム、ペットボトルや空き缶が見えてくる。ゴミを拾うということは地球環境をよくしているとか自分自身が気持ちいいということも当然ありますが、一番大切なことは【本当にきちんと見ようとしていますか?】ということだと思っています。従業員ひとりひとりのこと、家族のこと、子どものこと、地域にお住まいの方々のことなど、うわべだけで見聞きしていても見えないことの方が多いのです。プロキングが教えてくれることは、自分さえ見ようとすれば、きちんと見えたり感じたりすることができるということだと思います。
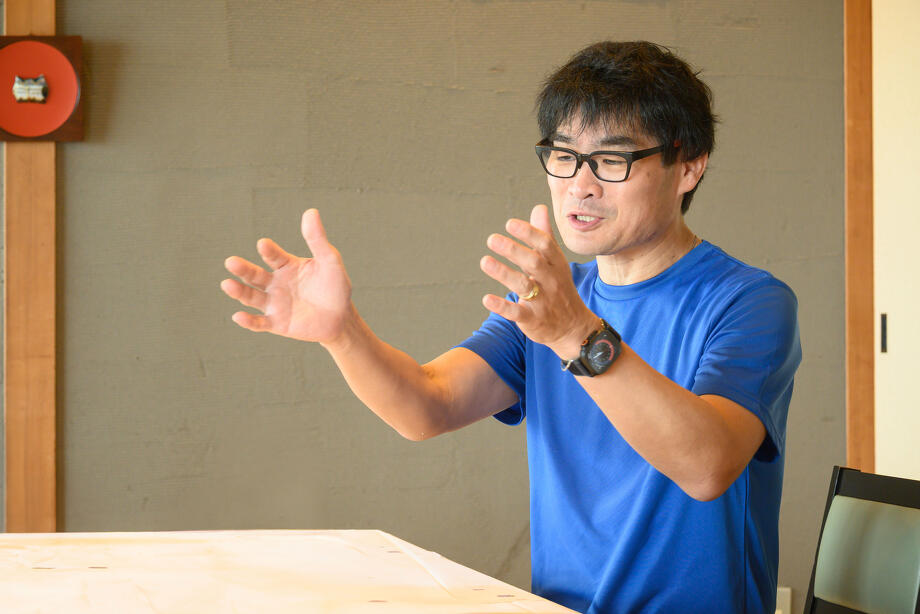
奥田:思わず膝を打ちました。この視点はまさに環境に対する意識や行動と重なると思います。環境問題はさまざまな視点から事実を見ようとしないと問題の本質が見えないことが多々あり、近視眼的な数字や事実だけを見ただけで極端な発想や偽善のような行動を起こす方もいます。わたしたち“あわいひかり”は、多様な視点で複層的な事実を丁寧に見つめ、深い洞察に基づいた考え方や視点を提言するよう心がけています。
5. そのSDG’s、楽しんでますか?
奥田:わたしたちも企業の取り組みとして海ごみクリーン活動などを実施していますが、本気でここ観音寺の自然豊かな環境や大切な海を後世に残していきたいという想いで継続しています。従業員が中心となって楽しみ、多くの人を巻き込みながら取り組むことで回を重ねるごとに地域の方々のご参加いただける方が増え、楽しみながら海をきれいにしています。
福﨑:こうした活動は自ら「楽しい」と感じないと絶対に続かないと思っています。大企業の中でもSDG’sと標榜して地域の清掃活動や木を植えるなどの活動を行っているところがありますが、参加している従業員の方が本当に「やりたい」と思ってやっているのか、時々疑問に感じることが正直あります。企業のCSRとして会社が「やれ」と言っているから仕方なくやっているのならそれは違うと思います。
プロキングもゴミ拾いをしながらジョギングをするという、ただでさえしんどいことをやるというモチベーションはやっぱり「楽しいから」なんです。マラソンを走っていると沿道から声援を送ってくださる方々がいらっしゃるから頑張れるように、プロキングはさらにゴミを拾っているので、たくさんの方々から励ましの声がけや感謝の言葉をいただけます。そうした声に支えられて「こちらこそありがとう」という感情が生まれ、参加者の皆さんとその気持ちを共有することで「また次もやろう」という気持ちが芽生えてくるんですね。
奥田:こうしたことは一時的なものではなく続けることで効果につながるものなので、続けていくためには「自らが楽しい」と感じることが最重要だと思います。環境に良いことなら暮らしや便利さを犠牲にしてでもやらねばならないといった極端な思想で取り組む人も中にはいらっしゃいますが、わたしたちがいきなり何百年も前の暮らしに戻れるかというと難しいですし、率直に「やりたくない」という感情が先に立ってしまいます。そうではなく、地球と長く共存していくために人が暮らす上でできることを考え、楽しみながら継続することで負担を減らし、最適なバランスを常に考え行動することが最重要なのだと思います。
福﨑:おっしゃるとおりで、なんでもかんでもプラスチックは悪という方がいらっしゃいますが、病院の点滴だって全部プラスチック容器に入っていますし、実はマスクだってプラスチック由来なわけです。これらは存在しないと生活が成り立たないわけで、全部無くそうということではなく、便利なものは活用しながら地球にやさしい処理を考えたり、いたずらにゴミとして捨てずリユースやリサイクルする活動を通じて対策していきましょうということが大切だと思います。
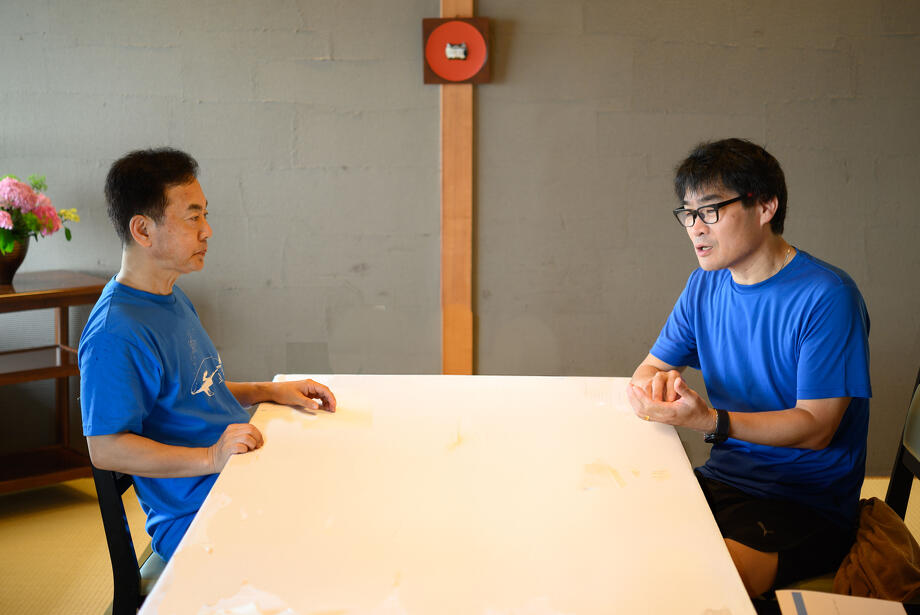
福﨑:今回はあわいひかり編集部の方々にプロキングにご参加いただきました。ここからまたプロキングをやってみようという輪が広がっていけば、街からゴミを捨てる人が減っていくと期待しています。仕事と直接関係のない人同士がひとつの目的で集まり、一緒に活動することでお互いを知るきっかけになれば、分断社会と言われている世の中がもっと暮らしやすく助け合えるようになると思います。
奥田:まさに「笑顔が循環する」ことにつながっていきますね。楽しくないと続かない、続かないとSDG’sとは言えない。とても示唆に富むお話をありがとうございました。

-

取材・文
森本 未沙(海育ちのエバンジェリスト)










