Event イベント

収穫されず、木になったまま放置された無数のみかんや木から落ちて朽ちてゆくみかん。産地ではよく見かける風景です。採らなくなった理由はいろいろあると思いますが、フードロスの削減が叫ばれている昨今、すこしでも食べ物を粗末にせず、有効に活用するために観音寺市にある観音寺第一高等学校の生徒4名が立ち上がり、規格外のみかんの皮を使ったクッキー作りを通してフードロス対策が行われています。どのような経緯で、このような活動が行われるようになったのか?あわいひかりが追ってみました!
「みKAN-ICHIプロジェクト」として課題発表
前回取材時、2025年2月に取り組みの発表機会があることは伺っていました。そして聞けばその発表会は一般からも参加申込が可能と…。なら行かない手はない!ということで2月某日、あわいひかり取材班は会場である観音寺第一高校へと赴きました。
その発表会は「SSH研究開発成果報告会」というもので、詳しくはこちらを参照ください。要するにみかんクッキーの取り組みを含めた、観音寺第一高校で行われた様々な研究結果を発表する場とのこと。その研究には、今回取材したフードロス問題のような社会課題を切り口にしたものもあれば、理系のアカデミックな取り組みなどもある様子。
あわいひかりとしては、いわゆるZ世代がどんな社会課題を感じているのか、どんな研究を進めているのかということを知り、今後の発信につなげたいという期待もありました。
そんな思いで発表が行われる体育館に足を踏み入れると…

すでに壁新聞形式の研究報告資料がずらっと設置されていました。タイトルを見ると「語彙力の発達を促す絵本作り」や「3秒ルールの安全性 〜食品の形状と菌の付着の関係〜」など、どれも興味を引く内容ばかり。社会課題系もあれば素朴な疑問に端を発しているものなど、学生ならではの自由さを感じました。果たして筆者は彼ら彼女らと同じ年齢だった頃、こんなこと考えていただろうか…と少し省みてしまいました。
研究発表はそれぞれのグループが資料の前で行うプレゼン形式でした。早速、みかんクッキープロジェクトのブースに行ってみると…
いましたいました。

発表のタイトルは「みKAN-ICHIプロジェクト 〜廃棄量を減らす魔法のクッキー〜」。
「みKAN-ICHI」とは今回作成したみかんクッキーのネーミングで、「KAN-ICHI」はこの観音寺第一高等学校の古くから親しまれている略称です。みかんと観一で「みKAN-ICHI」なわけですね、いい名前です。
プレゼンスタートの合図と同時に、しっかりと準備をしていたであろう発表が始まりました。なぜ規格外みかんを活用することになったのか、レシピ考案の紆余曲折、パッケージ作成の流れなどが簡潔に、しかし大事なところは数字も交えてわかりやすく伝えられていました。発表後は聴衆からの質問などもありましたが、それにも丁寧に回答をしていました。
フードロス問題に限らず、あらゆる社会課題はいろいろな要因が複雑に絡み合っていて、その解決は容易ではありません。しかしだからといって放置していい問題ではなく、様々なアプローチで取り組んでいく必要があると思います。この「みKAN-ICHIプロジェクト」もその一端であり、取り組んだ学生さんはもちろん、発表を聞いた他の学生たち、関わった大人たちなどは、真摯に向き合っていくきっかけを得たと思います。筆者も背筋が伸びる思いでした。
さて最後に、発表を終えたみなさん(プロジェクトメンバー4名)からお話しを聞く時間をいただきましたので、そちらの内容をお伝えして今回の記事の締めくくりとします。
あわいひかり:まずは本日の発表、お疲れさまでした。
学生一同:ありがとうございます。
あわいひかり:初期の段階から取材させていただき、今回そのまとめとなる発表を見て、なんというかわたしたちも多少なりとも貢献できたことがあるならよかったと感じました。
それでは少し過去の話にはなりますが、前回取材後から今日にいたるまでのところでいくつかトピックとなるものを伺っていきたいと思います。
イベント時に配布されたクッキーですが、以前見せていただいた試作品からだいぶ完成度が高まっていたように思います。どういった改良を加えたのでしょうか?

富山さん:レシピの改良に加えて、見た目も変更しました。当初はみかんを真上から見たようなイメージだったんですが、緑のアクセントを葉っぱらしくして位置を変え、横から見たイメージにしています。ぱっと見でよりみかんらしさが出せたかなと思います。

あわいひかり:なるほど、確かにみかん感が増しているのと、かわいらしさもアップしている印象ですね。
では次に、クッキー配布当日の感想、苦労した点やこんなことがあったということがあれば教えてください。
西谷さん:果たして人が集まってくれるのか?という不安があったんですが、いざ配り始めたらすごいたくさんの人が来てくれて、どんどん人が増えていって。それでクッキーを渡したときに「ありがとう」と言ってもらえて、とてもうれしかったです。
あわいひかり:そうですね、わたしも当日見ていました。まさに一瞬でしたよね。
西谷さん:むしろ来てくれないんじゃないかと思ってましたから、ほんとよかったです。
あわいひかり:知人や友人が来てくれた、であるとか、その後こういった反響の声を聞いたといったことはありますか?
西谷さん:祖母が来てくれていて、「クッキーおいしかったで」とか「ええパッケージやな」とか言ってもらえて。あぁよかったなあと思いました。
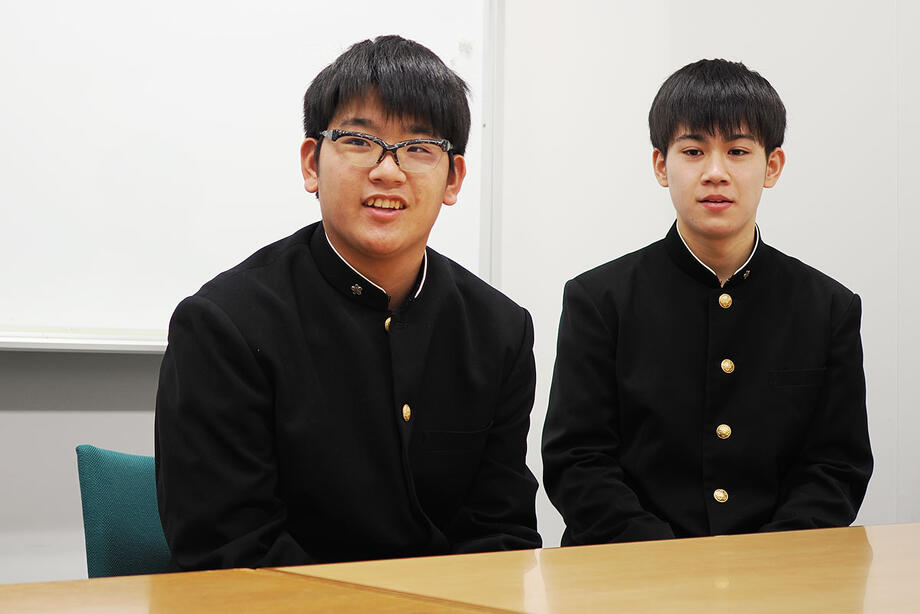
富山さん:今日の発表会も、新聞を見て※来てくださった方がいて、ぜひクッキーを作ってみたいという声をいただきました。そういう意味では、反響はかなりあったかと思います。
※クッキー配布の内容は地元紙でも記事として取り上げられていました。
あわいひかり:ありがとうございます。では、クッキー配布を終えて今日の発表までにもいろいろな出来事や苦労があったと想像します。いかがだったでしょう?
山口さん:途中、中間発表というのがあって、その時に先生からいろいろ指摘を受けました。その指摘内容をどうまとめるかというのが難しかったです。どうすれば伝わりやすくなるか、いかにコンパクトに収めるかなど、一番頭を使いました。

小滝さん:自分たちがやってきたことを余すことなく発表資料に落とし込まないといけなかったので、その点はとても苦労しました。
あわいひかり:そうですよね、自分たちの活動を過不足なく、且つわかりやすく伝えるって難しいと思います。でもよくまとまっていましたよ。
それでは最後の質問です。今回フードロス問題をテーマにした取り組みをされましたが、活動前と活動後の今とでは、意識に変化は起きましたか?
西谷さん:やっぱりテレビなどでそういったフレーズを聞くと「今取り組んでるやつやな」と反応するようにはなりましたし、食品を無駄に買わないようにしようという行動につながったりしています。
小滝さん:少しずれた回答かも知れませんが、たくさんクッキーを作る経験を経て、「少人数でたくさんのものを作る」ことの大変さが身に染みました。身近にあるお菓子なんかも、完成までに多くの手間がかかってるんだと思うと、すごいなと感じました。
あわいひかり:みなさん今回の経験から、本当に多くの学びを得たということが伝わりました。活動はここで一旦の区切りとなりますが、これからもフードロス問題への関心をもって、考えを巡らせていってくれたらと思います。
本日は本当にありがとうございました。
学生一同:ありがとうございました。

みなさん、やり遂げた顔をしています!
一連の取材を経て、若い世代が感じている課題、それに対して取り組もうとする姿勢を知ることができました。頼もしく感じる一方で、大人たちのツケを回してはいけないなとも思います。
筆者も、まずは賞味期限内にきちんと食べる!から徹底しようと心に決めました。
-

取材・文
矢野 豊(名映えプレイヤー)







